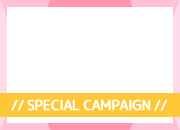ブログ
子どもに対して無関心
2025/04/16
不登校の子どもを持つお母さんは子どもに対して無関心な傾向があると聞いたことがあります。
カウンセリングをしていて、クライエントさんとその事について一緒に考えて話をしながら私はどうだったかなぁ?と振り返りました。
私の体験を振り返り
私の子どもが不登校だった時に、私は子どもに対して無関心だという自覚はありませんでした。
当時、子どもは高校生でした。だから私は子離れしなければならないし、子どもも親離れしなければ、と考えて色んな面で放っておいたり、任せたりしていました。それがお互いの為だと思っていました。
実際は放ったらかしにしすぎていたのか?あるいは、放ったらかしにした内容がズレていた?
そんな事は重要ではなくて、色々と考えて出てきたのは...
子どもに対して何かをしても、しなくても、根底に母の本当の愛があるかどうか。全く愛がないとは思いませんが、足りなかったような気がしています。これが今の私の最終的な答えです。
不登校を改善する為に、私は考え方や言動を変えていこうとしていました。その途中のどこかで、無関心をやめたと思います。それはどの地点だったのか?どうやって気付いたのか?自分の気持ちの流れを追っていくと...
無関心の対義語は「愛」
まずは、「無関心ではなくなった」とはどうなることか、無関心の対義語は何だろうと気になり調べてみました。すると「愛」でした。
「愛」🟰「大切に思う」🟰「関心を持つ」
母が忙しかったり視野が狭くなっていると関心の度合いが小さくなります。
私も気づかないうちにそうなっていたのかもしれません。
中学生くらいから、反抗的態度をとっていた子どものことを私は受け入れられず、好きになれませんでした。
しかし高校生になり、活発だった我が子が学校を休みがちになり、絶対に休むことのなかった体育大会を休んだり、大切な定期テストを受けられなくなったり、そんな様子を見て、とにかく私は子どものことを可哀想だと思いました。
可哀想過ぎて、もう子供と対立している場合ではない、やめようと。そしてどんな時も子どもの味方になり、寄り添っていこうという気持ちになりました。
その時から、子どものことを前よりも大切に思うようになりました。そして過保護ではなく、子どもに対して関心を持つようになりました。
憎たらしいことを言う子どもですが...
あなたは子どものことを大切に思っていますか?反抗ばかりで憎たらしいことを言うから好きになれない存在ですか?
子どもに対して無関心かどうか?一度、自分の心を見つめ直してください。これが不登校改善の為に、子どもが安心できる環境を作る為に必要です。
お母さんがクリアするテーマの1つだと確信しています。
心配症をやめられない
2025/04/09
不登校の子どもを持つお母さんで、どうしても子どもの心配することを止められないという方はいませんか?
心配を手放す
クライエントさんと何度か、カウンセリングを重ねてきて、初めにカウンセリングした時から、「心配は手放すようにしてください」と何度も最重要事項でお話してきました。
お母さんが心配ばかりしていると、それが子供のエネルギーをどんどん奪ってしまい、元気がなくなってしまうからです。
また心配して頭の中で「こうなったらどうしよう」と最悪な状況をイメージしたら、それを引き寄せてしまいます。
心配できないことがストレス?
それでもどうしてもやめられないようで、逆に心配できないという事がストレスになると言うクライエントさんがいました。
それだと何の為のカウンセリングか分からなくなってしまいます。
私は困り果ててしまいました。どうしたらいいのか?私から必要な話は全てお伝えしたはずなのに、それでも心配をやめられない?
今まで生きてきた何十年もの年月で積み重ねた考え方の癖は簡単には取れないです。
一冊の本との出会い
今回は改善不可能なのか?と半分諦めの気持ちで、今までの色んな資料をもう一度見直しました。
そして1冊の本を見つけました。それは約10年以上前に私がうつ病の一歩手前までいき、落ち込んでいた時に助けてくれた本でした。
『心配ぐせをなおせば全てが思いどおりになる』
著者・斉藤茂太
当時、私は何故か分からないけど、心配ばかりが押し寄せてきていました。
この本の中には、今の私のカウンセリングで大切にしている考えと同じようなことが分かりやすく書かれていました。
心配事を明確に
大切なのは心配事の内容をはっきりと明確にすることです。ノートに書くことで、心配な気持ちを吐き出すことができて、自分の頭の中も整理されていきます。
ただ心配だと書くだけでなく、何故心配なのか、どうしたらいいのか?など自分に問いかけ、考えながら書いていきます。
心配なことがあった場合はノートに書き出すか、人に話を聞いてもらうかのどちらか、あるいはセルフインタビューをすると言うのもありだそうです。
ノートに書くことの大切さは私も感じています。毎晩寝る前に1日を振り返り、その日の自分の感情にフォーカスしてみたり、感謝できた事を書いたり、日記のようにしています。
これをやっていると日々穏やかに暮らせる気がします。
不確定な状況を受け入れる
人はなぜ心配するのかというと、先に何が起こるかわからないからです。
この先に何が起こるかわからない不確定な状況は、生きていく上ではつきものですから、どんなに心配しても未来の不安は消えないのです。
そこで、未来ではなく、「今」にフォーカスしてみることをお勧めします。すなわち、自分が楽しい、充実している、幸せだと感じるために今の自分にできることを考えるのです。
これで心配から安心へと、少しずつでも気持ちが変化するのではないでしょうか?
子どもの本当の気持ち
2025/04/02
修学旅行のエピソード
母はいつも子どもの幸せを願っています。子どもの為と思って、一生の思い出になるからと、修学旅行だけは、なんとか行かせてやりたいと思ってしまいます。
修学旅行の日が近づいてくるのに、不登校の子どもの様子を見ていると今のままでは参加することが難しいだろうと、あるお母さんは思っていました。
もしもキャンセルするなら、早くしないと修学旅行のキャンセル料がかかってしまいます。
それが気になって、お母さんは焦って子どもに「修学旅行は行くの?」と聞いてしまいました。でも子どもはすぐに返事ができませんでした。
それだけで、もう言いたい事が十分伝わります。複雑な気持ち...
そして、仕事の休憩中、子どもから返事のメッセージが届いたそうです。
「行きたいけど、体力的に自信がないからキャンセルして...」そのメッセージを見て、聞かなければよかった、子どもに辛い決断をさせてしまったと、お母さんは心を痛めていました。
子どもの本音
「行きたいけど、行けない」これが不登校の子どもの本音だと思います。
他にも不登校の経験がある子どもさんから直接、話を聞いた事がありますが、その子の場合、なぜか分からないが、急に体調が悪くなるとのこと。
体調のいい時と悪い時があって、何がきっかけで体調が悪くなるのか自分で全く分からないと言っていました。
サボっているのでは?
カウンセリングを受けて回数を重ねていくと、お母さんの心も元気になっていき、同時に子どもも、少しずつ元気を取り戻していきます。
そして子どもの体調が回復していく途中の段階では調子のいい日が増えていきます。
家でいつも通りの生活ができるようになると、もう学校へ行けるのではないか?行けるのにサボっているのでは?と思ってしまいます。
でも、決してサボっているのではないと思います。学校へ行く段階までは、まだ子どものエネルギーが足りていないのです。
エネルギー充電
学校はストレスだらけの場所で、通学も授業もテストも友達付き合いも団体行動もあらゆることがストレスで、それを乗り越えるには、もっとエネルギーの充電が必要です。
その為にお母さんができることは、お母さんの心を安定させることです。そうする事で少しずつ子どもは確実に元気になっていきます。
そしてエネルギーが充分に満たされた時、お母さんが何か登校刺激などの働きかけをしなくても、子どもが自ら考えて、学校へ行くなどの行動を起こすようになります。放っておいても、子どもは動きたくなるのです。
心をコントロール
お母さん自身でなんとか心を安定させるのは、とても難しいと思います。私も最初は自分でなんとか心をコントロールしようとしました。
しかし、1人ではできませんでした。
その理由は
①きちんとコントロールできているかは、自分では判断が難しいから。
②ずーっと心を安定させるのは難しく、途中でイライラが爆発しそうになったり、急に不安に襲われるから。
だからカウンセリングでそんな時にどうしたら乗り越えられるかを、不登校の問題だけでなく、あらゆる場面で自分の心を安定させる方法をお伝えします。
不登校の子どもを持つお母さんと一緒に伴走して、そんな状況を乗り越えられたらいいなぁと思っています。
-
 マザーリーフの定例会参加
不登校親の会マザーリーフ奈良県大和郡山市を拠点に毎月1回公民館で開催しているマザーリーフの不登校親の会に参加
マザーリーフの定例会参加
不登校親の会マザーリーフ奈良県大和郡山市を拠点に毎月1回公民館で開催しているマザーリーフの不登校親の会に参加
-
 他人の言動に傷付きやすい人
子どもが不登校の時の話家では携帯を触っているかテレビを見ているだけの子どもを見て、家族はいつもイライラして、不
他人の言動に傷付きやすい人
子どもが不登校の時の話家では携帯を触っているかテレビを見ているだけの子どもを見て、家族はいつもイライラして、不
-
 どんなあなたも愛しています
条件付きの愛不登校で家にいてテレビばかり見て、ゲームばかりしている、そんな子どものことをお母さんは愛しています
どんなあなたも愛しています
条件付きの愛不登校で家にいてテレビばかり見て、ゲームばかりしている、そんな子どものことをお母さんは愛しています
-
 子どもの本当の気持ち
修学旅行のエピソード母はいつも子どもの幸せを願っています。子どもの為と思って、一生の思い出になるからと、修学旅
子どもの本当の気持ち
修学旅行のエピソード母はいつも子どもの幸せを願っています。子どもの為と思って、一生の思い出になるからと、修学旅
-
 心配症をやめられない
不登校の子どもを持つお母さんで、どうしても子どもの心配することを止められないという方はいませんか?心配を手放す
心配症をやめられない
不登校の子どもを持つお母さんで、どうしても子どもの心配することを止められないという方はいませんか?心配を手放す
カウンセリングルーム ムギ
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩まないでください。
電話番号:090-6367-6316
営業時間: 9:00〜17:00
定休日 : 不定休
所在地 : 生駒市俵口町 サロン情報はこちら